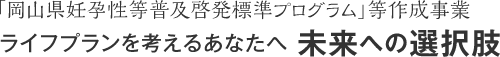プレコンセプションケア・100問ドリル
プレコンセプションケアに関する 100問に答えて知識をチェックしよう。
プレコンセプションケア・100問ドリルPDF版はこちら
健康な生活 パート1(体重,食事,睡眠,運動,寿命)【15問】
- 第1問
- BMIは,体重(kg)を身長(m)で2回割ることで計算できる.
- 第2問
- 「やせ」はBMIが18.5未満である.
- 第3問
- 「肥満」はBMIが25以上である.
- 第4問
- 妊娠する女性の「やせ」は生まれてくる子どもの低体重につながる.
- 第5問
- 生まれた時の体重が低い子どもは,将来,生活習慣病(高血圧,糖尿病など)になりやすい.
- 第6問
- 朝食を毎日食べることは良好な生活リズムと関係している.
- 第7問
- 朝食を毎日食べることは心の健康と関係し,高い学力・体力や良好な学習習慣と関係しているとされる.
- 第8問
- 睡眠時間の目安は,小学生は9~12時間,中学・高校生は8~10時間である.
- 第9問
- 思春期の頃から,睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌開始時刻が遅れ,夜寝る時刻が遅れ,朝起きるのが難しくなる人がいる.
- 第10問
- 夜ふかし・朝寝坊の習慣は慢性的な睡眠不足を伴い肥満のリスクになる.
- 第11問
- 睡眠の不調に,起立性調節障害(思春期前後に見られ,起立時にめまい,動悸などが起きる自律神経の失調)を合併する場合には,医師への相談が勧められる.
- 第12問
- 30分の運動を週に5回以上行うことが勧められているが,細切れの短い時間でも良いので,運動や身体活動の時間を作れば効果を得られるとの報告もある.
- 第13問
- 青少年 5~17歳は,平均で1日60分の身体活動,1週間に3日は高強度の有酸素運動(ウォーキング,ジョギング,ダンスなど)や筋力や骨を強化するトレーニングが推奨されている(WHOの「運動・身体活動」に関するガイドライン(2020)).
- 第14問
- 妊娠中や産後の女性は,1週間で150分程度の中強度の有酸素運動が推奨されている(WHOの「運動・身体活動」に関するガイドライン(2020)).
- 第15問
- 2022年の日本人の平均寿命は男性81.05歳,女性87.09歳であるが,さらに重要な「健康寿命」はそれぞれ約9年,約12年短い.
健康な生活 パート2(タバコ,アルコール,薬物)【11問】
- 第1問
- 青少年期に喫煙を開始すると,成人後に喫煙を開始した場合に比べて,がんや虚血性心疾患などの危険性がより高くなる(肺がんでは,20歳未満で喫煙を開始した場合の死亡率は,非喫煙者に比べて5.5倍).
- 第2問
- 吸い始める年齢が若いほど,ニコチンへの依存度が高く禁煙が困難になることが多い.
- 第3問
- 喫煙者の男性では,陰茎への血流が減り勃起しにくくなることがある.
- 第4問
- 喫煙者の男性では,精子の数や運動率が低下する.
- 第5問
- 喫煙は女性にとって,不妊症や妊娠後の流産のリスクを高くする.
- 第6問
- 喫煙者の女性は閉経が早まる.
- 第7問
- 妊婦の喫煙で「死産や乳児死亡が約2倍」「出生時体重が96~200g低下」「子どもの11歳時の身長が1.5~2.0cm低い」「子どもの肥満や糖尿病の率が上昇」などの報告がある.
- 第8問
- 妊婦の喫煙や赤ちゃんの出生後の周囲の人の喫煙は乳幼児突然死症候群(SIDS)の要因となる.
- 第9問
- 妊婦の飲酒は,赤ちゃんの低体重,顔面を中心とする形態異常,脳障害などを引き起こす可能性がある(胎児性アルコール・スペクトラム障害).
- 第10問
- 薬物を乱用すると.家族や友達とのコミュニケーションもできなくなってしまうことがある.
- 第11問
- 脳の発達する小・中・高校の時期に薬物を乱用すると「感情のコントロールがきかなくなる」「意欲がなくなる」「怒りっぽくなる」など,心身の発達が損なわれる.
健康な生活 パート3(HPV・子宮頸がん,性感染症,がん)【11問】
- 第1問
- ヒトパピローマウイルス(HPV)は子宮頚がんの原因になる.
- 第2問
- HPVに感染しただけでは自覚症状はない.
- 第3問
- HPVワクチンの接種による予防が重要である.
- 第4問
- 小学校6年~高校1年の女子は無料でHPVワクチンの接種ができる.
- 第5問
- 9価のHPVワクチンで子宮頸がんの原因となるHPVの80~90パーセントを防ぐことができる.
- 第6問
- HPVワクチンを接種したうえで,子宮がん検診をすることが重要である.
- 第7問
- 男性がHPVワクチンを接種することで,中咽頭がん,肛門がんなどの予防が期待でき,性交によるHPV感染から女性を守ることにつながる.
- 第8問
- クラミジア感染症は,卵管を傷つけるため不妊症の原因となる.
- 第9問
- 避妊用ピルとコンドームを併用する「デュアル・プロテクション(二重の防御)」で,避妊と性感染症予防の効果が高くなる.
- 第10問
- 定期的に健康診断・人間ドックは,病気の早期発見のみではなく,生活習慣の見直しにつながる.
- 第11問
- がんの罹患数の順位(2020年)では,女性の乳がんは第1位,子宮がんは第5位(最近は子宮がんの約4割が子宮頸がん,約6割が子宮体がん),男性では前立腺がんが第1位である.
健康な生活 パート3参考資料
ライフプラン パート1(精子,卵子,年齢と妊孕性,不妊症,不育症)【20問】
- 第1問
- 女性も男性も年齢が高くなると子どもができにくくなる.
- 第2問
- 女性の卵子の数は胎児の頃に約700万個と最も多く,出生時には約200万個,思春期には20~30万個に減少し,50歳頃の閉経時にはほとんどなくなる.
- 第3問
- 女性の「卵巣年齢」は実際の年齢とは異なることがあり,AMH(抗ミュラー管ホルモン)の血液検査は「卵巣年齢」を推定する上で参考になる.
- 第4問
- 基礎体温は目盛りの細かい婦人体温計を使って起床時に舌の下で測定する.
- 第5問
- 基礎体温で低温期と高温期がある(二相性)場合には,排卵があると考えられる.
- 第6問
- 「やせ」は骨粗しょう症の原因になりやすい.
- 第7問
- 女性の「やせ」は月経不順や無月経の原因になる.
- 第8問
- 妊婦の「やせ」は,赤ちゃんの低出生時体重につながる.
- 第9問
- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は月経不順のため不妊の原因になるとともに,糖尿病や高脂血症にもなりやすい.
- 第10問
- 月経痛などの月経困難症や月経の量が多い(過多月経)場合は,子宮内膜症を疑う必要がある.子宮内膜症は不妊症の原因にもなる.
- 第11問
- 不妊症の原因の半分は男性の方にもある.
- 第12問
- 精巣内の温度が高くなると精子数や運動率の低下につながるため下半身を温めすぎたり,下着などで圧迫しすぎたりすることは避ける.
- 第13問
- 不妊のため,検査や治療を受けたことのあるカップルは4~5組に1組とされる.
- 第14問
- 人工授精は女性の排卵のタイミングに合わせて,洗浄した精子を子宮内に注入する方法である.
- 第15問
- 体外受精は,ホルモン剤で卵巣を刺激し,卵胞を育てたうえで針を刺して卵子を取り出し,精子をかけて体外で受精させる方法である.培養して発育した受精卵(胚)は凍結保存しておき1つずつ解凍して子宮に戻して妊娠を期待する.
- 第16問
- 体外受精による妊娠率は20代,30代前半では2~3割であるが,40歳では約1割になる.
- 第17問
- 日本人の初婚年齢は,2022年は男性31.1歳,女性29.7歳であるが,2000年は各28.8歳,27.0歳,1980年は各27.8歳,25.2歳であった.
- 第18問
- 女性の妊娠時の年齢が高いほど,染色体異常による流産率,生まれてくる子どもが染色体異常(ダウン症など)を持つ率が高くなる.
- 第19問
- 2回の流産を経験する「不育症」の女性は約5%(20人に1人)とされる.
- 第20問
- 流産や死産を繰り返した場合には,不育症のリスク因子(原因)を検査するとよい.
ライフプラン パート2(妊孕性温存,養子縁組,里親制度,提供精子・卵子,SRHR,LGBTQ,SOGI)【13問】
- 第1問
- 抗がん剤を使用すると,卵子や精子が少なくなったり,なくなったりすることがある.
- 第2問
- 抗がん剤を使用する前に,卵子や卵巣,精子などを凍結保存しておき,将来の妊娠に備える方法がある(妊孕性温存).
- 第3問
- 健康な女性が,年齢が高くなってからの妊娠に備えて若いうちに卵子を凍結保存すること(妊孕性温存)に対して助成金を出している自治体がある.
- 第4問
- 高齢になってからの妊娠では,妊娠高血圧症候群などの病気が起こりやすくなる.
- 第5問
- 普通養子縁組,特別養子縁組では,法律上の親子関係になる.
- 第6問
- 里親制度では,法律上の親子関係は生じない.
- 第7問
- 生まれつきの病気や抗がん剤治療,あるいは,加齢により,自身の精子や卵子により妊娠しなくなった場合に,精子や卵子の提供を受けて生殖医療(不妊治療)をして子どもを持つことが行われている.
- 第8問
- 日本においても,提供精子や提供卵子による生殖医療を規定する法律(特定生殖補助医療法案)が議論されている(2025年3月現在).
- 第9問
- セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(SRHR)では,自分の身体は自分のものであり, 性的な行動をとるかとらないかは自分で決められることが求められている.
- 第10問
- セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(SRHR)では,いつ,誰と,結婚するか,結婚しないか,子どもを持つか持たないかを選べることが求められている.
- 第11問
- 性の要素は,身体の性,社会から割り当てられた性,性自認(自分は男,女,どちらでもない,どちらでもある等の認識),性的指向(男性が好き,女性が好き,両方好き,どちらも好きにならない等の気持ち),性別表現(男性的,女性的な服装や髪型など),性役割(男性として,女性としての役割)など,多岐にわたる.
- 第12問
- それぞれの性の要素にはグラデーションがあり,すべての人が多様な性の要素を持っている.
- 第13問
- 生まれたときに割り当てられた性(戸籍の性など)と性の自己認識(性自認)とが一致しないトランスジェンダーのうち,医療施設を受診することで性別違和感が楽になる例がある.
ライフプラン パート2参考資料
ライフプラン パート3(妊娠,出産,育児,ワークライフバランス)【17問】
- 第1問
- 母子手帳は,妊娠,出産,育児に関する一貫した健康記録であり,妊娠届を出すときにもらえる.
- 第2問
- 重症のつわり(妊娠悪阻)では点滴治療などを必要とする.
- 第3問
- 妊婦に歯周病があると,早産や低出生体重児のリスクが高くなる.
- 第4問
- 流産や早産をしそうな状態である切迫流産や切迫早産では,仕事を休んで安静にしなければならないことがある.
- 第5問
- 妊婦の血圧が上昇する妊娠高血圧症候群では,胎児の発育が不良になったり,母体の痙攣が起こったりすることがある.
- 第6問
- 妊娠中に糖尿病となった女性は,産後に治っても,将来,糖尿病になりやすい.
- 第7問
- 妊娠中に胎児に病気がないか調べる方法として,出生前診断(胎児診断)がある.
- 第8問
- 妊娠初期に妊婦の血液を調べることで,胎児の染色体異常がないかを推定する方法がある(NIPT:非侵襲性出生前遺伝学的検査).
- 第9問
- ダウン症の子どもは発達がゆっくりしているが,感受性が強く、陽気で思いやりがあるなどの特徴がある.
- 第10問
- 出生前診断で胎児の異常がわかった場合,妊娠を続けない選択をするのか悩むカップルも多い.
- 第11問
- ワーク・ライフ・バランス(WLB)とは「仕事と生活の両立」のことであり,その向上は,生活の充実につながる.
- 第12問
- ワーク・ライフ・バランス(WLB)の向上は,企業にとっても,従業員が定着し離職率が低下する,モチベーションや生産性が向上する等のメリットがある.
- 第13問
- 出産後の1年間にうつになる母親は約10%とされる.
- 第14問
- 子どもが生まれた後の夫・パートナーにも約10%にうつが見られる.
- 第15問
- 母親も父親も産休や育休を取得できて職場復帰しやすい働き方ができることは重要である.
- 第16問
- 2022年から産後パパ育休が始まり,子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得可能になった(分割して2回取得も可能).
- 第17問
- ジェンダー・ギャップ指数(GGI)は,世界経済フォーラムが,経済,教育,健康,政治の各分野の男女の平等性を数値化したものであり,日本の順位は低い(2024年は146か国中118位).
子どもを持ちたいと思った時の準備(葉酸,風疹ワクチン,治療薬,遺伝)【6問】
- 第1問
- 葉酸を,食事に加えてサプリメント(1日400μg)を妊娠1か月以上前から妊娠3か月まで摂取することで,胎児の神経管閉鎖障害のリスクを下げる可能性がある.
- 第2問
- 妊娠初期(20週以前)に妊婦が風疹にかかり胎児に感染すると,赤ちゃんが耳や眼,心臓の病気(難聴,白内障,先天性心疾患)を特徴とする先天性風しん症候群を持って生まれてくる可能性が高くなる.
- 第3問
- 風疹ワクチンは妊娠中には打てないので,妊娠を希望する場合には,風疹の抗体検査を受けて抗体価が低い場合には,妊娠前に風疹ワクチンを接種して,妊娠中の感染を予防する.
- 第4問
- 妊婦への風疹の感染を防ぐため,夫・パートナーや家族も風疹の抗体検査を受けて,抗体価が低い場合には風疹ワクチンを接種する.
- 第5問
- 妊娠中に飲むことができる薬と飲むことができない薬があるので,妊娠を希望したら,その病気の担当の医師や産婦人科医,薬剤師とあらかじめ相談しておく必要がある.
- 第6問
- 自身やパートナーの家族・親族に遺伝的な病気がある場合には,遺伝に関する専門的な知識を持つ医師やカウンセラーに相談することができる.
危機の回避(デートDV,性的同意,避妊)【7問】
- 第1問
- 付き合っている人に,LINEなどでメッセージを送ったときに,すぐに返信(即レス)がないと責めるのはデートDVの一種である.
- 第2問
- 一度,ハグやキスなどを経験した間柄であっても,そのたびに同意を確認することが必要である(性的同意).
- 第3問
- 布団や畳,床などに陰茎(ペニス)をこすりつけるのは不適切なマスターベーションである.
- 第4問
- 経口の避妊薬(低用量ピル)を飲み忘れた,コンドームが破れたなどの場合に,緊急避妊薬(アフターピル,緊急避妊ピル)をできるだけ早く内服すると(遅くとも72時間以内),妊娠を回避することができる.
- 第5問
- 緊急避妊薬を内服しても妊娠することがあるため,また,性感染症になることもあるため注意が必要である.
- 第6問
- 性交があった場合に,避妊をしていなければ,また,避妊をしていても100%ではないので,月経が遅れたら妊娠かどうかを確認する.
- 第7問
- ピア・プレッシャー(仲間からの圧力)により,性的な話題に参加させられたり,性的な体験の告白をさせられたり,ノリや罰ゲームなどで裸にさせられたりキスなどの性的な行為をさせられたりすることがないよう,他人の人権,そして自身の人権を尊重する必要がある.