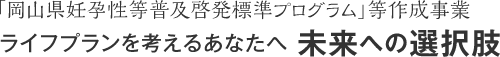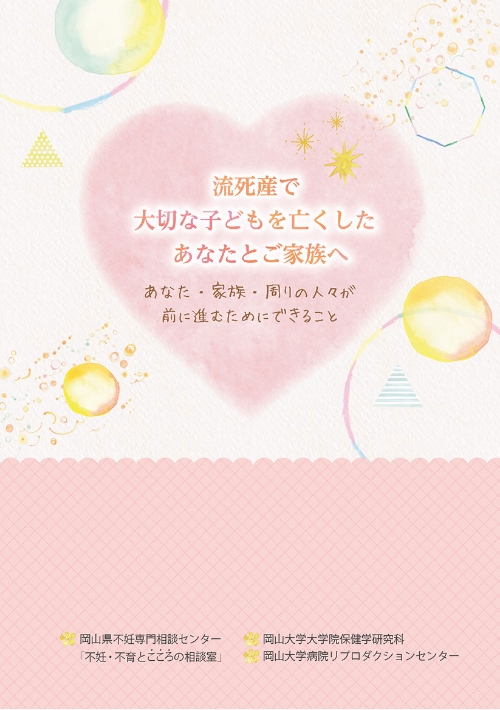流産や死産を繰り返す不育症、
そのリスクになるのは?
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して子どもを持つことができない場合は、不育症と呼ばれます。
一般的には流産・死産を2回経験した場合には(一部の死産では1回でも)、また、子どもは助かっても妊娠周期の割に小さかった場合にも、リスク因子(原因)を調べることをお勧めします。また、1人目が正常に生まれていても、その後に流産や死産を繰り返した場合は、やはり、続発性不育症として検査をし、必要であれば治療を行います。
不育症のリスク因子(原因)はさまざま
厚生労働科学研究班による不育症のリスク因子別の頻度を円グラフで示します。子宮の形が正常とは異なる子宮形態異常、甲状腺の異常、カップルのどちらかの染色体異常、抗リン脂質抗体症候群、凝固因子の異常などがあります。
糖尿病や甲状腺ホルモンの異常が見つかった場合にはその治療を行います。抗リン脂質抗体症候群や凝固異常では、妊娠中に、抗凝固療法(低用量アスピリン内服やヘパリン注射など)を行う場合もあります。
不育症外来を受診した方は、適切な対応を受けることで最終的に約80%が出産に至るとされています。


不育症の治療は
リスク因子に合わせて行います
子宮形態異常
子宮の内腔に壁があり左右に分かれている中隔子宮などでは、子宮鏡による手術を行うことがあります。
抗リン脂質抗体症候群
カルジオリピンなどのリン脂質に対する自己抗体ができ、胎盤や血管を攻撃して流産や死産につながったり、胎児の発育に悪影響があったりします。母体も、血圧が上昇したり、血管がつまってしまうこと(血栓)があります。
このため、妊娠中に低用量アスピリンやヘパリンなど、血液を固まりにくくする薬剤を使用します(抗凝固療法)。
その他の血栓性素因が
ある場合や、
抗リン脂質抗体症候群の
判断基準に含まれていない
抗リン脂質抗体が陽性の場合
担当医と相談の上、抗凝固療法を行うかどうか決定します。
夫婦の染色体異常
比較的高率に流産となりますが、無治療でも、一定の確率で赤ちゃんを得られます。ご希望があれば、遺伝カウンセリングを受けて説明を聞くことができます。また、施設によっては、体外受精をして受精卵の一部を取って異常の有無を確認する検査(着床前検査)を実施しています。
甲状腺機能異常
甲状腺ホルモンの低下は流産のリスクを上昇させます。必要な状態であれば、妊娠前から甲状腺専門医のもとで適切な治療・管理を行ないます。
リスク因子が特定
できなかった場合
リスクが特定できない場合は、今までの流産は偶然の胎児染色体異常を繰り返していた可能性もあります。
しかし、流産回数が多い場合は、まだ検査できない異常を持っている場合もあります。
男性が原因の不育症もある?
男性に染色体異常がある場合にも不育症になることがあります。
また、精子のDNAの断片化が増えると流産につながるとされます。
肥満や喫煙を避けて、生活習慣を改善することで精子の状態も改善することが知られています。
不育症の治療の成功率は?
適切な治療方針が決まれば、不育症カップルの約80%が、最終的に元気な赤ちゃんを持つことができているというデータがあります。
4回までの流産であれば60%以上が次の妊娠でうまくいっているとされます。
もし、治療をしても流産した場合は、胎児の方に偶然の染色体異常があったかどうかを確認することは、次の治療法を考える上で、非常に重要です。
不育症カップルの
精神的なサポートは?
流産や死産となったときには、つらい気持ちになりますし、それが「うつ」や「次の妊娠への不安」につながることがあります。
多くの医療施設でグリーフケアやテンダー・ラビング・ケア(TLC)と呼ばれる精神的サポートが行われ始めています。
病院のスタッフや不妊専門相談センター、また、不育症の当時者支援グループ、流死産の当事者支援グループなどにお問い合せ下さい。